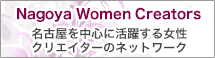菊之助による菊之助【伝統芸能の継承者たち】
知らざぁ言って聞かしやしょう!この決め台詞で有名な歌舞伎の演目「白波五人男」を観に行ってきた。約一ヶ月の公演で、さぞ芸が醸成しているだろうと思うと、今月のバカみたいにバタバタした日々もなんのその。前日の夜もせっせと原稿を書き(こうゆう時は筆が進む!)、今日の楽を迎えた。今回の御園座は、顔ぶれに人気役者が少なかったからか、なかなかチケットが売れずにご苦労されたと聞いている。お名前とお顔が一致する役者さんが少なかったのは事実だし、役どころによっては、ううむ、なぜこの人が?と思うお方もいらっしゃったのだけど、こと菊之助さんに関して言えば、芸が醸成するのをしっかり待った甲斐があった。
菊之助さんは若手の人気役者で、人気が先行しすぎて、まだ線が細い感じがしていたのだけど、今日の弁天小僧では黙阿弥の江戸弁を見事にこなし、私の印象は一気に変わった。弁天小僧が最後に追いつめられるシーンで、印象的な仕草を見た。着物を上半身脱いでいる菊之助さんは、立ち回りをする最中、早業でさっと着物の後ろを引っ張って帯に入れ込んだのである。確かに着物の後ろが少し垂れていてきりっと締まっていなかった。そのため、胴裏の朱色が目立ってしまい、後ろ姿が決まらないのである。果たしてあれだけ激しい立ち回りをしていて、こんなところに気づくだろうか?きっと菊之助さんには後ろにも目がついているに違いない。ささっと着物を直した後、"弁天小僧菊之助"は切腹して息絶えた。菊之助さんによる"菊之助"の素晴らしい舞台に感激した私は、お隣の菊之助ファンらしきおばさまにわからぬよう、そっと涙をふいた。
それにしても美男というのは得ですよね〜。菊之助さん、本当にいいお顔なさっている。お姫様の役も色男も、そして弁天小僧のような江戸弁の不埒者も美しく決まっちゃう。私が中学生くらいの時に映画になったジュリーによる天草四郎の「魔界転生」を思い出してしまった。
歌舞伎となると着物姿のお客さんが多くなるので、いろんな方の素敵なお着物姿を拝見できるのも楽しみの一つ。今日もお着物の方がとっても多かったです。私は、弁天小僧に合わせて、一番上の写真の着物で。帯は雷神の刺繍。真冬に締めたくなる柄。
こちらは今日の御園座とはまったく関係がないのだけど友人の着物姿。紅型の美しい青に細かく花模様が入っている見事な染め。今日、このお着物に一見似ているなと思ったご婦人を見掛けたので、もしや?と思わず近寄って観察しちゃった。階段を追いかけてぴたっと寄り添うように歩いてしまい、完全に不審者でした。ふふふ、でも私の友人の着物の方がずっときれいな染めでした。なぜだか自慢げになる私。着物好きの視線はすぐにわかりますからね〜。ばれないようにさりげなく観察しないとね。
さぁて、楽しみにしていた歌舞伎を堪能した日曜ももう終わり。明日はまた新幹線と電車を乗り継ぎ、有馬温泉方面に出掛けてきます。しばらくは旅芸人の日々が続くのである。もう寝なくっちゃ。