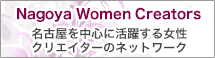利休にたずねよ【読書する贅沢】
市川海老蔵主演の映画「利休にたずねよ」の試写会に、映画ナビゲーターの松岡ひとみさんがご招待くださった。↑左が映画パンフレット、右が小説文庫本↑ 山本兼一さんの直木賞受賞作である同名小説は先に読んでいたので「読んでから観る」かたちとなった。何十年も前の某出版社の小説と映画の同時PRキャッチコピーに「読んでから観るか、観てから読むか」というのがあったけど、私は完全に読んでから観る派。小説と映画を比べちゃうと、想像力が働く分どうしても小説に軍配があがってしまうので、本当は観てから読んだ方が、作品への思いは深くなるのかもしれないな、と思っている。ところが映画「利休にたずねよ」に関して言えば、読んでからでも観てからでも、どっちでも楽しめる作品だなぁと珍しい感想を持ったのである。小説の方は、利休の人生をいろいろな人の視点で切り取ってオムニバスのような仕立てになっているので、人間関係が立体的な構図となって見えてくる。映画はその仕立てではないけれど、主役である海老蔵の圧倒的な演技力と存在感が、新しい利休像を作り上げていて興味深く観てしまったのだ。海老蔵が利休ってどうなんだろ?なんて素人考えでいたのだけど、ひとかたならぬ美への執着者・利休と、狂気を秘めた海老蔵は、どこかで重なり合っているように思えた。
もちろん、利休の映画となればお茶のお点前やお道具がとっても気になるところなので、そういう意味でも楽しめる。なんと、長次郎作の黒楽を楽家から特別に借りることができ、その黒楽茶碗で100年ぶりにお点前したシーンが映し出されている。海老蔵のお点前のシーンはさすがに所作が美しい。背中に筋がはいっているかのような伸びや手配りのきれいさなど、これは歌舞伎役者たる所以かな。ロケ場所も仕事柄気になるところで、大徳寺や南禅寺などビックリするような場所で行われている。お茶については、三千家がパートに分かれて監修されたそう。敬愛する茶人であり歴史学者の熊倉功夫さんも監修に名を連ねている。つまり、茶道界がお互いに睨みをきかせながら、それぞれに(表向きは)納得して出来上がった映画というわけである。この裏話を聞いただけでも、監督はじめスタッフの方々の並々ならぬご苦労と気遣いがあっただろうと拝察する。
原作を読んでいる立場でもし希望を言えるとしたら、ぜひ監督に聞いてみたいことが2つある。ひとつは、原作と明らかに異なる演出をした最後のシーンについて(これ以上はネタバレになるので書けないけど)。女性の視点では、いまいち納得しがたいものがあったなぁ。もうひとつは、若い時代の利休のエロティシズムについて。映画では若さゆえの傲慢さは描かれていたが、エロティシズムの部分は出てこなかった。千利休のイメージが崩れるとかなんとか言われそうで、茶道界との関連があったのかもしれないけど、なぜそこを描かなかったのか、是非とも聞いてみたい。
ちなみに気になる配役。利休が市川海老蔵、信長に伊勢谷友介、秀吉が大森南朋、長次郎を柄本明。利休の最後の奥さんの役を中谷美紀、ねねが檀れい。豪華な配役ですな。さて、映画「利休にたずねよ」は12月7日から東映系で公開だそうです。まだまだ時間がたっぷりあるので、ぜひ小説を読んでから映画を観てみてくださいまし。