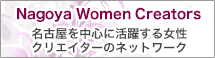ヴィヨンの妻【読書する贅沢】
読んでから見るか、見てから読むか。
角川書店が派手な映画事業に乗り出した時のキャッチコピーである。
小学生だった私は、このコピーの意味に深くうなづきながら、「犬神家の一族」「人間の証明」「野生の証明」を読みふけり、薬師丸ひろ子と高倉健の演技に涙した。映画だけではなく、テレビドラマにもなったんじゃなかったかな。小説を読ませ、映画も観させるというメディアミックスを広告展開した最初の成功例だったと思う。
映画評論家でもなければ小説家でもないので、とても生意気な意見ではあるが、原作の小説を超える映画はない、というのが私の思い。主人公の顔立ちや声を想像しながら、商業的損得のない物語展開を楽しむことのできる小説と、すでに誰かが原作を勝手に解釈して作り込んだ映画とでは、想像力がまったく違ってくるからだ。映画を観てから小説を読むと、「なんか違うんだよな〜」と偉そうな言葉を吐くことが多いので、なるべく生意気なオンナにならないよう、必ず小説を読んでから映画を観るようにしている(ここまでの流れで、もうすでに十分生意気なオンナではありますが)。
はてさて、それで今日観て来たのが「ヴィヨンの妻」。原作は太宰治の同名小説だ。この映画の名古屋におけるPRをお隣の由美さんがお手伝いしているということで、「ちゃんと観てね〜」と言われていたにも関わらず、公開ぎりぎりの今日になってしまった(由美さん、遅くなってごめんなさい、こんなことなら最初から私一人で見に行けば良かったわん)。
もちろん、新潮社から文庫化されている原作を読んでから映画にのぞんだ。太宰治自身の心中未遂や幾多の女性遍歴についてはここでは棚上げするとして、太宰治の文章の美しさには確かに心惹かれるものがあり、原作を読み進むにつれて「このきれいな文章を映画にするとしたら、どんなになるだろう?」とそればかりを気にかけて小説を読むことになってしまった。(この長い文章、太宰っぽさ出てますかね???まさかね、あはは、ただ長いってだけじゃね・・・)
それで、映画を観た感想は・・・。のっけから「美しい文章」が「美しい話し言葉となって台詞で生きていた」のである。松たか子と浅野忠信の夫婦のやりとりなどは、本当に美しい言葉だなぁとうっとりしてしまった。戦後まもないあの時代に、日本人はあんな美しい言葉で話していたのだろうか。
(こういう感想をもったということは、この映画に関して言えば、原作のイメージとあまりかけ離れていないという判断にもなる)
というわけで、「ヴィヨンの妻」は公開期間があとわずかとなってしまった。もしもまだご覧になっていない方がいらっしゃれば、是非、新潮文庫の原作を読んでから(短編なのですぐに読めちゃいます)、美しい太宰ワールドを堪能しに映画館に足をお運びくださいませ。オススメでございます。