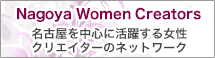かの名はポンパドール 佐藤賢一【読書する贅沢】
家庭画報に連載されていた「かの名はポンパドール」が、今月号で最終回を迎えた。フランス王ルイ15世の籠姫であり、聡明で美しい女性として、そして今に伝わるフランス文芸の保護者として有名なポンパドール侯爵夫人のことを、その実弟であるマリニィ侯爵の目で描いた小説である。
ポンパドール夫人は、趣味の良い目利きにより多くの芸術を育ててきた。当時のヴェルサイユに渦巻いた「ア・ラ・ポンパドール」は現代にまで引き継がれたひとつの価値観となっている。
パリのホテル・ド・クリヨンはルイ15世が夫人のために作らせた館であるし、大統領府であるエリゼ宮は夫人自ら設計したものである。
さらに、ワイン好きの方ならご存知だと思うが、かのロマネコンティは、ポンパドール夫人とブルボン王朝の名族コンティ公がその所有権をめぐって争い、結果コンティ公のものとなって、ロマネコンティの名が付けられたもの。
さらにさらに、かのシャトー・ラフィット・ロッチルド(ワタクシがこの世で最も愛するワインであります)は、ロマネコンティ争いに破れたポンパドール夫人が怒ってヴェルサイユからブルゴーニュワインを閉め出し、代わりに愛飲したワインなのだ。
このポンパドール夫人、当然ながら良くも言われるが、悪くも言われている。佐藤賢一さんは、そのポンパドール夫人を、実弟であるマリニィ侯爵の目線で描くことで、崇高な誇り高き女性として見事に表現しているのだ。
家庭画報の連載を読む楽しみが、今月で終わってしまうのは少しさびしいけれど、最後の最後まで、ポンパドール夫人の潔い生き様を読ませてもらえたので、とても心地よい思いで満たされている。
ちなみに佐藤賢一さんといえば、直木賞作品「王妃の離婚」が有名で、私もその本が最初の佐藤作品となった。フランスの歴史小説に特化した小説家として、史実に忠実に、けれど独自の視点と創作を加えて仕立てられた小説は、時間も忘れて読みふけってしまうほど素晴らしいものばかりだ。中でも私がいつも「うなる」のは、カタカナ表記の少なさである。
フランスが舞台の小説なので地名や人名にカタカナ表記があるのは必然であるが、形容詞などにほとんどカタカナを用いないのである。見た目にも実に美しい文章だ。昔から使われていた言葉を用いて古い時代を表現することこそ、歴史小説の理想型なのではないかと思わせてくれる。