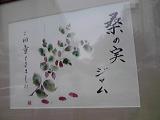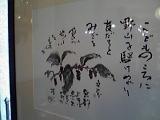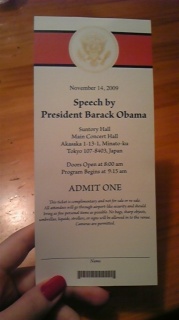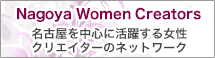料理の星【今日の地球】
東京ミシュランが華々しいデビューを飾って早2年。今年はとうとう日本の料理の聖域とも言える京都や大阪にも進出し、編集長ナレ氏の辣腕を歓迎する向きも、眉をひそめる声も挙がっているとか。かくいう私もミシュランにはかつて随分お世話になったし(フランスではレストラン情報だけでなく旅の友としての役割もあるので)、東京ミシュランが出た時は、行った事のあるレストランの星を意味なく足したりして喜んでいた。
星の増減で、人生を左右されるシェフがいるほど、一部の料理界では恐ろしいほどの権威を持ってしまったミシュラン。その他方で、ミシュランの存在など関係なく、地元の旬のものを美味しく調理し、地元の人々に喜んでもらうことを人生の最大の喜びとしている料理人たちが、この日本にはたくさんいる。
そんなことを思いおこしたのは、おもてなしの心で腕をふるう料理人に出逢ったからである。およそ7年ぶりに取材で博多を訪れた私は、福岡出身の飲み友達・サイトーサンから「コストパフォーマンス日本一のお寿司屋があるから行って来て!」と教えてもらったお店に出向いた。
オーダーしたのはサイトーサンおすすめ3,000円のコース。3,000円ですよ、3,000円!内容は、お口取り、大皿のお刺身盛り合わせ、季節のお料理2種、おまかせ握り6カン、お汁物、デザートである。またそのお刺身やお寿司のネタの新鮮なことと言ったら!穴子のあぶり刺身、季節の鯖、ヒラマサ、イカ、アンキモ・・・。お寿司の方は、江戸前風にすべて仕事をしてから卓上に出され、それぞれの味の違いが際立つように工夫されていた。時折、料理人の方がわたしたちの卓の様子を見て気にしてくださってるのがとても印象的だった。お話したらきっと面白そうだな〜。玄界灘の美味しい旬が集合したお皿に、大満腹大満足してホテルへ戻った。
本当に美味しいものを食べようと思ったら、やっぱり地産地消が一番なのだなと実感した一夜だった。だって地元で獲れた新鮮なお魚は地元で消費するべきだもん。東京や名古屋まで輸送するのにガソリンや電気を用い、コストをかけてCO2を排出し、値段が高くなってしまった食事って意味あるのかしら?
そんなことを思いながらホテルで寝転がっていると、サイトーサンから電話が入った。とても美味しかったという感想と礼を述べると、サイトーサンが言った。「銀座のあのお寿司屋さんもいいだろうけど、博多の寿司屋は違う意味でいいでしょ!あのお店のコストパフォーマンスの素晴らしさを分かってもらえて良かったよ!」と。銀座のお寿司屋さんとは、ミシュランに登場しているお店のことである。
芸術品のように美しく、計算され洗練された料理を都会でいただく事もそれはそれで素敵だけれど、わたしたちがこれから大切にしていきたい料理とは、その場所で獲れた食材をその場所で美味しく食べること、なんじゃないのかな。
サイトーサンおすすめのお寿司屋さんは、「すし処 寿楽」でググっていただければすぐに分かります。近々、[200字で綴る美味の想い出]にて更新しようかと画策中。博多へ行かれる方にはイチオシのお店です。サイトーサン、今度ぜひご一緒しましょうね!ちゃっちゃきちゃらじぇ〜。(覚えたての博多弁、合ってます?)