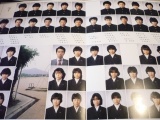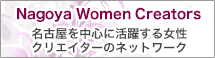襟元を正す【徒然なるお仕事】
10年来、関わっているキモノの本「和煦」のモデル撮影が来週に控えている。この撮影でモデルさんを選抜する時にいつも大きな課題になるのが、「背の低さ」である。出来上がったキモノをお借りして撮影するため、そのほとんどが一般女性の背の高さで仕立てられた物ばかり。モデル事務所のモデルさんたちは一般女性よりもうんと高い人が多いので、キモノに合わせた背の低いモデルさんを探すのがひと苦労なのだ。
この日は、「和煦」のためのモデルオーディションだった。ユカタを着てもらい、キモノ姿になるとどんな雰囲気になるのかをカメラテストする。さらに直接お話して、キモノの仕事キャリアの有無や個人的にキモノを着るかどうか、などなど多少の質問をして、そのモデルさんの持っている空気感とかキャラクターを探るのである。一度に何人も、多い時は何十人ものモデルさんと対面するが、オーディションのたびに「肌きれいだな〜」とか「この子、好み〜。きゃ〜わい〜な〜」と私はついついオヤジ目線で見てしまう。
カメラテストと面談が終わると、今度はスタッフだけで、どのモデルさんにするのかを話し合う。その号の企画に見合うよう、女性っぽい感じがいいのか、モダンに仕上げたいかなど意見を言うのだ。その会議中に、カメラマンのなぎさがつぶやいた一言がとても印象に残った。「彼女(オーディションに来ていたモデルさんの一人)さ〜、ちょっとした仕草とか座り方とかがだらしがなかったよね。あんなに可愛いんだし売れっ子だからもったいないね〜。いずまいがきちんとしていれば、印象って全然違うのに」
なるほどね〜。確かに顔が可愛いとかスタイルが良いだけじゃなくて、しゃきっとした上品な立居振舞をすれば、魅力はう〜んとアップする。そして、これは外見を売り物にしているモデルさんたちだけじゃなくて、すべての仕事をする人にも当てはまる「マナー」なんじゃないかしら、と、ふと思ったのである。
インタビューや取材などで、初対面の人と話をすることが多い我々コピーライターだって、もちろんそうだ。たとえコピーが素晴らしい仕上がりだとしても、会った時の印象が良くなければ、コピーの評価も引き算されてしまうだろう。逆に、印象が良いと、後日仕上がったコピーから匂いたつような品のようなものを感じてもらえるはずである。
あぁ、こうして書いていて自己反省ばかりが頭をよぎる私。匂いたつような美しい文章のためには、美しい立居振舞が必要なのでございますなぁ。明日から取材旅行に出ることもあり、早速、襟元を正して、お仕事に向かうことをここで誓わせていただきます。