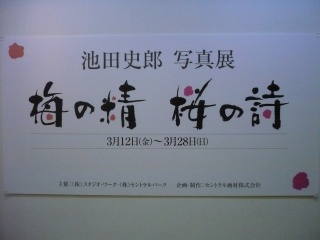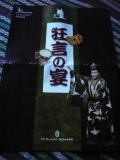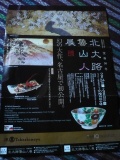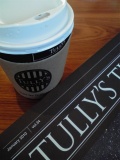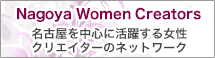スイーツ天国!【えとせとら】
先々週、友人のフリーアナウンサー・加藤千佳ちゃんのお誕生日パーティーが開催された。場所は、クッチーナ・イタリアーナ・ヤヤマ。我が家から徒歩数分のイタリアンで、千佳ちゃんセレクトメニューもあり、美味しく楽しい会だった。彼女はアナウンサー業のかたわら、スイーツやパンのサイトを主宰していることもあり、その夜はなにかとスイーツが話題になった。
オーナーシェフの矢山氏が千佳ちゃんのために作ったバースデーケーキはメガサイズのショッキングピンクイチゴケーキだったし(シメシャンはロゼを用意していけば良かったぁ〜と後悔しきりでした)、某T島屋でオープン直前だったドーナッツがお目見えするし、シフォンケーキで有名な某F社の新商品も試食できちゃったりした。
こちらが某T島屋に17日にオープンしたばかりのドーナッツ。なんでもオープンした日は千人あまりの行列ができたという話だけど、すごいですよね。T島屋の独身ナイトハンター・ナナちゃんがばっちりアピールしていた。
そしてこちらは、フレーバーの新商品「マーナズ・グラノラ」。(ボケボケでごめんなさい!)岩田社長自ら説明してくださり、口卑しい私は食事中にもかかわらず早速味見させていただいた。見た目はビスケットっぽいけど、実際いただいてみるとシリアルをぎゅっと凝縮した感じで、美味しいんです。オートミール・ブラウンシュガー・メープルシロップだけが原材料だと岩田社長はおっしゃったけど、どうやって固めるの?と素朴な疑問がわいたので聞いてみた。
「シリアルのでんぷん質を利用して固めてるんですよ〜」とのことで、これまたびっくり。余分な物が一切入っていなくて、噛み締めるほどに自然の甘みをじんわり感じることができる。普通のシリアル感覚で牛乳かけちゃっても良さそうだし、岩田社長いわくヨーグルトとの相性も良いのだとか。これもT島屋のフレーバーで買えるそうです。
というわけで、千佳ちゃんバースデーは、私も大好きなスイーツ話とワイン話と美味しいお食事やお店情報、さらには一部エロトークも混じり合って、楽しく不思議にコーフンした一夜だった。お食事やワイン、そしてエロスはすべて繋がっている、とどこかのゲージュツカがおっしゃってたなぁと思いつつ、それがどなただったのかを思い出せないままに、千鳥足で久屋大通を北上して帰路についたのだった。一体誰だったんだっけか???
こちらは、これまた某T島屋に1月末から並び始めたワタクシの大大大好きな豆大福!東京上野の岡埜栄泉から、なんと毎日入荷しているというんだから、T島屋のスイーツ根性にはたまげた!下町上野の銘菓と言えば、岡埜栄泉の豆大福とうさぎやのどらやきと昔から決まっていて、上野の美術館に行く時にこの大福のことを思い出し、どうしてもガマンできなくって豆大福を買い、上野公園のベンチで食べちゃうのが私の数少ない至福の時間である。江戸では町民文化が発達したから、今でも銘菓と言えばおせんべいや大福などの庶民派おやつが美味しいのだ。京都は上品な生菓子や干菓子ですよね、やっぱり。
岡埜栄泉は、根岸にも谷中にもあって(別々の経営らしいんだけど)、特に谷中のお店は構えもご店主のおじさんも昔の風情たっぷりで大好きだ。いつか、名古屋へお土産に持って帰りたいとおじさんに告げると、「うちのはね、やわらかさが売りなんだから、絶対に今日中に食べてくださいよ」と江戸弁でまくしたてられたことがある。何が美味しいって、そのおじさん言う通り、日持ちはしないが塩味がしっかりきいた皮のやわらかさ、そして餡のコクと味わい深さだ。T島屋さんのご努力のおかげで、この豆大福を毎日でも買うことができるのだから、本当に新幹線とT島屋の企画担当の方には感謝感謝である。(一回前のコラムには確か地元で獲れた物を地元で消費するべし的な記事を書いているっつうの!)あ、上野のうさぎやは、大学時代の同級生・谷口クンが家業を受け継いでいるお店でございますので、こちらのどらやきも名古屋駅のT島屋で買えるようになったりしちゃったら嬉しいなぁと思う今日このごろである。