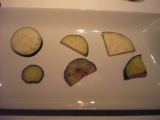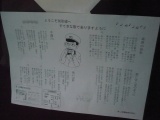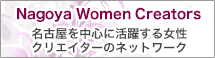なす・ナス・茄子!【おうちごはん】
もう2週間も前のことになるが、麗しき女性3人の野菜ソムリエ集団・ラヴェリアンのお野菜勉強会に参加してきた。今回のテーマはナスで、その勉強会ではナスの種類や特徴などを学びつつ、ナスづくしのお料理をいただくという内容。会場は私のセカンドタウンである円頓寺商店街近くのフランス料理店「ペルージュ」だった。↑の写真は、左から。短なす、水なす、賀茂なす。
3種類のナスを、生と焼いた物で味比べ。
生ならどれが美味しい(好み)か。
焼いた物なら、一番はどれか。
私の好みは、生→水なす。焼いた物→賀茂なすでございました。
手モデは、
この勉強会に誘ってくださった
お隣の由美さん〜♬
と、そんなわけで、ナスには驚く程たくさんの在来品種があるということ、油と相性の良いナスの油吸収率を下げるためには塩水で洗うといいということなど、すぐにでも役立つ豆知識が満載の楽しい会であった。ラヴェリアンの麗しき女性、えこさん・くみこさん・みきさん、ありがとうございました。さて、オベンキョーすると、これみよがしに実践したくなるのが私の癖である。
でもって、来週末のユカタ会の最終打ち合わせのために、我が家で戦略会議(結局ただのご飯会になっちゃったけど)幹事3人が集まった時のこと。スタイリストの原結美さんと、ヘアメイクの村上由見子さんとで、あーだこーだとガールズトーク炸裂しつつも、しっかりナスをいただいたのである。水なすを生のままカットし、塩水で洗い、水をきったら、塩・バルサミコ・オリーブオイルをかけて簡単サラダ。それと最後に白なすで作った麻婆ナス。白なすは、加熱すると皮が緑色になった。やわらかい食感と淡白な味わいが、麻婆にはぴったりでございました。せっかく作ったのに、写真を撮り忘れてしまったので、メニュー写真は由見子さんのOh!Tiaraブログをご覧ください。
そういえば、春に宇宙旅行へと出掛けてしまった重兵衛さんでは、毎年この季節になると水なすのぬか漬けを出してくださった。それがさくさくしてとびきり美味しかったなぁ〜と今は亡き大将を思い出していたら、またまた涙が出ちゃって仕方ない。ふ〜、いつまでひきずるんでしょうね(泣)。
そして、我が家の食材が豊かなタイミングで
なぜか必ず現れるこのオトコ。
甥っこノゾムと共に、
水なすのサラダをお酒のアテに。
そして今年お初の松茸、いただきもの♬
お醤油を刷毛で塗って、さっと炙って、
お酒のアテアテアテ。
「香り松茸」を十分に楽しんだ。
スーパーの店頭では、春でも冬でも夏野菜のはずのナスが並んでいる。ハウス栽培のおかげではあるが、やっぱりナスが美味しくなるのは夏本番の今であって、春や冬ではない。ナスの種類ごとに調理法を変えて楽しめるのも今の季節だけなのだ。現に、大阪で生産される水なすは今しか流通していない。野菜に季節がなくなってしまったと嘆く向きも多いようだけど、そんな大流通経路に対抗するかのように、在来品種を頑張って生産してくださる農家の方がたくさんいらっしゃるのだ。嬉しい限り。そんな農家の方たちを応援する意味でも、今年もたくさんいろ〜んな種類のナスを食べ尽くしまする。店頭に珍しいナスを見かけたら、皆さんも是非お試しになってください!