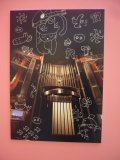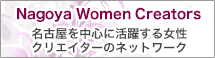山里のおもてなし【今日の地球】
8月のはじめに長野県飯山市へと取材に出掛けてきた。豪雪・仏壇・お寺で有名なこの街に地元の人形作家の美術館がオープンしたということで、その作家の先生の取材だったのだ。早朝に名古屋・栄で集合し、ロケバスにて信州へ。名古屋から約4時間、プロのドライバーさんの安心の運転に体をまかせていたら、お昼前に飯山市に到着した。何度もこのコラムに書いているけど、信州の空気ってどうしてあんなに違うんでしょうね?何かが違う。山並みだって美しい。田んぼにもそこはかとなく品があるように見えるから不思議だ。
取材相手の人形作家さんは、予想以上に気さくで予想通りに情熱的なお人柄で、インタビューそのものは非常にスムーズに進んでいった。作り手の気持ちに短時間でいかに入り込むかが作家や職人の取材の時には重要な要素となるので、最初の質問はいつも前日から考えておくのだけど、この日は作家さんからビンビン伝わってくる情の強さを感じ、思い切ってディープな質問からぶつけてみた。それが功を奏したのかどうかわからないけれど、作家さんの心の内側を少し覗けたような気がする。
山里の田舎の風景に作品のインスピレーションを受けるという先生が、取材陣の私たちにお茶請けで出してくださったのが、↑の写真の「ほおずき」である。美術館のカフェと言えば、オリジナルクッキーやらフレーバーティーなどでオシャレなセットを勧めるのが普通だけど、この飯山市というロケーションを鑑みて、あえて「山里のお百姓さんが日頃食べているおやつ」をお茶請けとして出しているのだそう。お恥ずかしながら、ほおずきなんて、食べたことがない私は、物珍しくて3個もいただいてしまった。ちょっと酸っぱいトマトみたいで、美味しかったですぞ。こういうおもてなしっていいですよね〜。気取ってなくて、その土地の空気感を感じ取れて。観光資源を目標にしている日本の地方は、こんな風に地元の普段の暮らしをおもてなしとして推奨していくべきなんじゃないのかな。地名が入っているだけのどこにでもあるようなお菓子とか、ワケわかんないお土産品とか作らずにね(苦笑)。
取材を終えて帰り道。今回は取材陣の女子チームの強い要望により、道の駅オアシスおぶせに立ち寄っていただいた。だって信州にせっかく来たなら、しかも栗で有名な小布施まで来てるのなら、栗かのことかペーストとかどら焼きとかアイスクリームとか栗ごはんとか、買っていきたいですよね〜!
(どんだけ買うんだ?って顔をしてた人もいましたが)
信州の農家産直の野菜がとっても安く販売されていたので、こっちもしっかりチェック!桃3個・オクラ2パック・赤パプリカ2個を買って800円の安さ。この時に買ったオクラが、大きくて表面の毛が薄く、シャキシャキしてとっても美味しかったのだ。焼きびたしにしてペロっといただきました。あ〜、やっぱり信州ロケ取材ってだいすき〜〜〜〜!!!!!