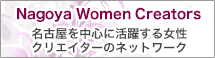中村時蔵さんの歌舞伎舞踊【伝統芸能の継承者たち】
10月の楽しみと言えば、やっぱり御園座の顔見世でございます。10月は季刊発行の編集物が一斉に動き出す時期ということもあり、取材やら下調べやらでなにかとバタバタする一ヶ月なのだけど、あらゆる用事よりも最優先させるのが顔見世である。今年は歌舞伎座の建替えをしていることもあり、地方公演の役者の層が厚いので、余計に期待がふくらむのだ。御園座の場合、坂田藤十郎や尾上菊五郎などの大御所をはじめ、尾上菊之助といった若手人気役者が揃っている。
そして、なんてったって私が大好きな歌舞伎役者の一人。
中村時蔵さんも出演されているのであります!
女形を務める時蔵さんは、とりわけ舞踊が素晴らしい。
今迄、時蔵さんの舞踊を拝見して、何度感激し涙を流したことか。
円熟期を迎えられた時蔵さん、どんな舞踊を見せてくださるかしら。
時蔵さんの舞踊は「舞妓の花宴」。三変化舞踊と言われるもので、途中で小道具や衣装を変えながら、踊り手が移り変わってゆく舞踊であった。間がとっても難しく、踊りに盛り上がりがイマイチないので、時間が長い割には地味と言えば地味な舞踊だった。それでもさすがに時蔵さんの踊りは、やっぱり魅せるんですねぇ。体のしなりや品の良い所作、立ち姿の綺麗なラインには、自然と視線が吸い寄せられてしまった。特に、男踊りから恋する娘へと変化するあたりは、とても50代とは思えない可愛さに満ちていて、ほぉ〜と深く息をついてしまった。こういう舞踊を拝見すると、本当に心がすぅ〜っと透き通るような気持ちになる。やっぱり伝統芸能というのは、私たちのDNAに擦り込まれた美学を刺激するんですねぇ。
この他、藤十郎さんの政岡役や、菊五郎さんの身替座禅、菊之助さんの弁天小僧を気持ち良く拝見して、芸能に恵まれた秋の夜は更けていった。あ〜あ、名古屋でも毎月歌舞伎やってくれないかな。そしたらきっとお小遣いはすべて歌舞伎に費やすのに。
御園座には、この格好で。
紅型の少し渋めの着物に、ピンクの織帯、グリーン系統で小物をまとめて。
着物のハッカケがきれいなサーモンピンクだったので、帯とは合ってたと思います。紅型の着物に、紺、ピンク、グリーンが入っているので、合わせやすいんですね。
↓なせかここから「おうちごはん」のコラムに早変わり!
備忘録代わりということでご容赦くださいませ↓
この日は日曜日の夜の部だったので、出掛ける前にはらごしらえは松茸ご飯で!今年豊作だという秋の味覚をいただいたので、おあげさん・しめじ・ちょっぴりお醤油で炊きこみました。