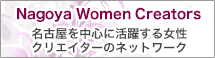それにしても寒いですね〜毎日。寒さに滅法弱いワタクシは、ヒートテックで上下を固めております。3週間前に30度のバンコクにいたなんて、もうシンジラレナ〜イ。ってことで、再びバンコクの旅日記でございます。
バンコクに旅した一番の目的は姪っこアユミに会うため。そして2番目の目的はなんといってもタイ飯!野菜とフルーツが豊富なタイ料理は、辛いところだけを除けば大好きなジャンルである。現地の人々がフツウに食している美味しいお店をアユミがリサーチしてくれているはずなので、そういうごくフツウなタイご飯が楽しみだった。
結論から言うと、やっぱりタイ料理はヘルシーで美味しい!そして、屋台で食べても、ちょっと高いレストランで食べても、材料の使い方や味の整え方はほとんど一緒だということがよくわかった。味の基本は酸・甘・辛のバランスだ。特に甘みについてはグラニュー糖で加糖していたのにビックリ。中華料理のように化学調味料をふんだんに使うということもないので、舌にやさしい。そしてなにより興味深かったのは、原始的な調味の方法である。原始的という表現が正しいかどうかはわからないけど、少なくとも飽食日本の進化しすぎたとも言える調味と比較すると、極めてシンプルなのだ。
シンプルな調味ということでは、カレーが一番わかりやすかった。←これはアユミがどうしても私に食べさせたいと連れて行ってくれたお店のカオソイというカレー麺。食べた瞬間に懐かしさが広がった。多分わたしたちが子供の頃に食べていた、カレー粉から炒めて作る原始的なカレーの味なのだ。今の日本のカレーって、やたらマイルドでコクがあって煮込んだ美味しさを強調しているけど、昔食べていたカレーって、こういう味だったよな〜って思えるものだった。多分、カレー粉(お店でブレンドしているとは思うけど)と小麦粉を炒めて、チキンスープで割って、チキンを入れてさっと煮込んだもの。だからコクもないしマイルドなんかじゃ全然ないし、ピリっと辛くてスパイシーで、でもスパイスの調合の良さが体にじんわり効いていく感じ。写真はあまり美味しそうに見えないので残念なんだけど、これ、あんまり美味しいのでお代わりしちゃったんですよね。中に茹で上がった麺がカレーとからまっていて、上に揚げた麺がのっかっている。その食感の違いを楽しむのも面白いし、お漬け物とライムがついてくるのでそれを入れて酸味を足してもまた美味しい。あぁ、もう一回食べたいな〜。

アユミと同じ名古屋大院生でバンコクのユネスコにインターンとして来ているイチタロくんとアユミと共に屋台でカンパイ〜♥

こちらは蟹のカレー炒め、プーパッポン。これまた絶品!アユミの友人Qちゃんから教えてもらったタイ料理の名物なのだそう。

これはちょっとすましてレストランで食べたサラダ。柑橘系のフルーツと海老をサラダにするのもタイ料理の特徴みたいだ。これはベトナムにも同じようなサラダがあったな〜。

とあるレストランでおねだり猫が出現。シャム猫の国だけあって、どんな野良猫もシャムのようにスマートで頭が小さく、高貴な顔をしているように思えたんだけど。

これが美味しい屋台通り。トンローという街にありました。イチタロくん、ホスト役をありがとう!

カオソイのお店で、調味料に籠がかかっていた。こういうの、昭和っぽくて懐かしいですよね。

日本食に飢えているアユミへのお土産のひとつ、不二屋のミルキーロール!これ以外に、お土産には鮎の甘露煮やさんまの山椒煮なども持参したのだ。

小さい時からペコちゃんの真似をよくやってたので、一応おさえておきましたw

お寿司大好きなアユミと日本食レストランで。
こんなバンコクの熱さと美味を記憶の片隅に置きながら、今週はひたすら寒いところばかりに出張しておりました(コラム更新が遅れた言い訳です)。前半は三河湾に浮かぶアートの島、佐久島へ。港から渡船に乗り、島について漁船に乗り換え、揺れに耐えつつ取材敢行。コピーライターってホント体力勝負だわ〜。一瞬名古屋に戻ったのだけど、翌日に今度は信州・松本へ。中央線が北上するに従って車窓の風景は雪になり、松本は激寒の雪景色だった。潮風と寒風によってお肌はぼろぼろのワタクシ。今宵はバンコクで買ったスパイスを炒めて、3週間前の記憶を呼び起こし、南国の料理で心と体を癒そうと思っている。