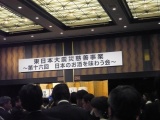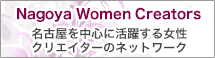北方領土にヒゲが生えた【今日の地球】
ドアップ写真で大変失礼いたします。
↑そうなんです、ワタクシ、ついにヒゲが生えました↑
目線がオヤジになってるだの、思想はオッサンと一緒だの、友人からは完全に中年オヤジとしてカウントされているワタクシ。それでも一応女子部に所属しているつもりでいたのですが、とうとう、というか、ついに、ヒゲが生えちゃったのであります。唇の右下ににょろっと生えている黒い線、見えますよね。数日前に鏡を見て気づいたこのヒゲ。唇と顔面皮膚のちょうど境目に生えてきている。写真では皮膚上に生えているように見えるけど、実際は唇のピンク色と皮膚色を境にするライン上にあるのだ。テニスで言えばオンラインってやつですな。地図で言えば北方領土みたいなもので、所有権を主張し合えば結論が出しにくくなる場所である。そして、これまた不思議なことに、ヒゲを発見してから2日後の今日、改めてヒゲを観察しようと鏡をのぞくと(ヒゲは伸ばしっぱなしになっていた!)、あら不思議。自然にヒゲは抜け落ちてなくなっていたのだ。引っ張った覚えもなければ、抜いた記憶もないのだけど、あのヒゲはいつ抜けちゃったんだろうか。
実は、ここのところface bookのお友達リストの件で、もやもやとした思いを持っていた。Aさんとお友達になってるとBさんが良く思わないとか。Bさんとお友達だったものだから、できればお友達登録したくないCさんからリクエストが来ちゃって困ったとか。あと、お仕事先の人だったりすると、いろいろと人間関係があるじゃないですか。長年親しくしている業界の先輩は「快く思っていない人なら、承認しない方がアナタのためだよ」と普通なら言いにくいことをちゃんと教えてくださった。ふむふむ、その通り。face bookの恩恵で素敵な方と出逢うこともできたから、やっぱり面白いツールなんだけど。面倒だなぁと思うことも多くて。こんなことならホントにプライベートなおつきあいの人だけをお友達承認すれば良かったな〜とちょっぴり後悔。子供の時は「あの子と仲良しにするなら仲間に入れてやんない」な〜んて、他人を自分の所有物みたいに扱っていたことがあったけど、オトナになるとそんな子供じみたことは言ってられない。でも他人に対する所有意識というのは、オトナになっても心の奥底では持ち続けているものなのだ。たとえそれが男女の関係ではなく、純粋に友情で結ばれている友達同士だったとしても。
みんなが無意識に持っている友人に対する所有意識も、私のオヤジヒゲのように自然にするりと抜け落ちちゃえば、面倒な人間関係や内輪もめなんかに発展しないのになぁ。ま、あまり深く考えず、八方美人的にお友達承認しちゃった私が悪いんですけどね、はい。