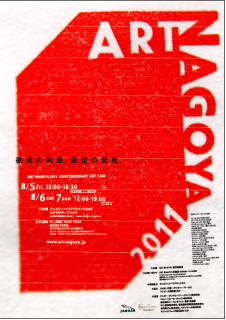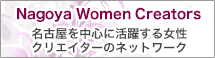もっと!地酒の会【一杯の幸せ】
「逸品もっとよくなるプロジェクト」のメンバーではじめた「もっと!地酒の会」の定例会第3回が去る5月19日におこなわれたというのに、なんと第4会の定例会が明後日7月7日に迫っているではありませんか!関係者の皆様、申し訳ございません。議事録代わりのコラムアップがすっかり遅れてしまいました。そんなわけで、第3回の報告をしつつも、第4回のお知らせまでしちゃうという一挙両得のコラムとさせていただきまする。↑上の写真は第3回の時のもの。この時のゲスト酒蔵は、愛知県江南市の「勲碧酒造」さん。そうです、4月に酒蔵開放にお邪魔し、さんざん呑んで酔っぱらってしまったあの酒蔵さんでございます。この地酒の会は、日本酒の知識をつけようとか蘊蓄を語ろうとか、そういう難しいお勉強の会ではない。どちらかというと初心者向けに、日本酒って美味しいんだ!お料理と一緒にいただくと楽しみが広がるんだ!ということをお互いにわかちあう会なのである。なんせ主催者である私たちが日本酒の初心者なのだから、蘊蓄など語れるはずがないのですけれどね。そこで毎回、最初に酒蔵メーカーさんの方に、その酒蔵について、歴史や文化的背景や、商品の特徴などをお話いただくことにしている。上の写真はその時のもの。ワタクシ、思い切り鏡に映りこんでますね。地酒の会には時間が許す限りはお着物でお出掛けしております。この日は、祖母から譲り受けた結城紬の単衣でした。
この会から、ほんの少し、バージョンアップして。
当日のお料理の内容に合わせて、
日本酒を飲む順番を酒蔵さんに選んでいただいた。
お品書きと共に皆さんのお手元に配られる。
これがいただいたお酒たち。
全体の印象としては、毎日お母さんが作ってくれる晩ご飯に
お父さんが何も考えずに晩酌するのにピッタリなお酒、という感じ。おばんざい系によく合うんじゃないかな。
左は「逸品もっとよくなるプロジェクト」の主宰であり、
「もっと!地酒の会」の主宰でもある、
我らが岡田新吾氏。
右が勲碧酒造の村瀬専務でございます。
さて、そして明後日7月7日は第4回が開催される。今回は福井県の「越の磯」さん。まだ若干名のお席はなんとかなりそうですので、もし参加ご希望の方がいらっしゃったら、「もっと!地酒の会」の申込フォームよりメールをお送りくださいまし。私にご連絡くださってもOKです。
今回は偶然にも七夕の開催。彦星さまと織姫さまが一年に一度出逢えるかどうかはお天気次第なのであるが、美味しい日本酒と夏限定の地ビールのラインナップ、そして「和蕎楽」の美味しいお料理とは確実に出逢うことができる。しかも季節感たっぷりで、なんと鮎の塩焼きも出るというじゃありませんか。小さい頃から長良川の鮎を食べて育っているので、鮎には目のない私。もう今から楽しみなんでございます。蛇足な話なのだけど、実は先週末は立て続けに実家でゲストをお迎えし、岐阜市内で昼→夜→昼と外食が続いた。今の岐阜では季節柄どのお店でも鮎が出される。見事に3軒とも鮎の塩焼きが出たので(もっともそのうちの2軒は鮎専門店だったのだけど)、たった2日で合計12匹もの鮎をいただいてすっかり鮎腹になってしまった。ところが明後日も鮎が出ると聞いてもまったく違和感なく楽しみにできるのは、本当に鮎が好きなんですね、私。さぁて、明後日は、どんなお酒と鮎を組み合わせていただけるのか、想像をめいっぱいふくらませて、地酒の会にのぞもうと思っている。