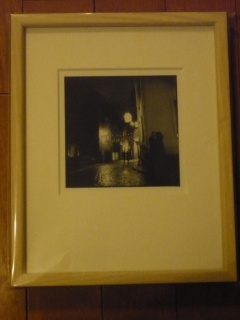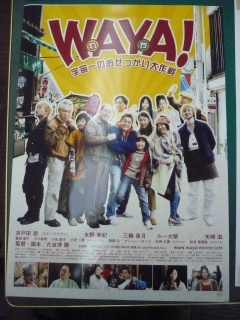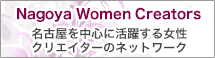約1時間40分の妄想劇【えとせとら】
明日の取材のための前入りで、今日から東京に来ている。打ち合せやら雑務をバタバタとこなし、新幹線に飛び乗ったのは夕方になっていた。夏休みだからか、まだお盆休みの人が多いからか、車内は満席で立つ人もいるほど混み合っていた。私はいつもの[2人席の通路側]を指定していたので、その座席に向かうと、なんとそこにはギターケースが置かれているではありませんか。お隣の窓際の席に座る男性の持ち物らしいので「あのぉ」と声をかけると、「あ、座ります?」と聞かれ、心の中で「あったりまえでしょ?指定とってるんだから」とつぶやきながらも、顔ではニッコリ笑って「えぇ、すみません」と外面良く答える私。自分の荷物を棚に上げようとしていると、その男性はギターケースを抱えて座ったまま窮屈そうに体勢を保っていた。なにも大きなギターケースを抱えなくても、棚には十分なスペースがある。親切心のつもりで「上に置けますよ・・・」と声をかけると、その彼はきっぱりと「いえ、大丈夫です」と答えた。なんだか変な人だなぁ。
おもむろに荷物を片付け、お茶と本をテーブルに置き、新幹線での佇まいを整えた私は、ふと足元を見て再び驚いた。お隣の彼は、ギターケースが床に触れないように、自分の靴の甲の部分にタオルを載せ、その上にギターケースを置いて抱きしめているのである。な、な、なんですと???ギターがそんなに大切なのか?この人は。それとも新幹線の微妙な振動がギターに不具合を与えるんだろうか。さらに30分が経過しても、その人は姿勢を保ったまま、ギターケースを抱えて座っていた。
妄想好きな私は本を読むふりをしながら、お隣の男性の人生についていろいろなことを思いめぐらすことにした。妄想1→地味な格好をしているけど有名なギタリストで、京都あたりで演奏活動をして東京に戻る途中。妄想2→ギターのコレクターで、関西のオークションで珍しいギターを手に入れたばかり。妄想3→実は中身はギターではなく、今高騰している金塊が入っている。中身が金塊だと思うと、俄然ドキドキしてくるから不思議だ。う〜ん、楽しいなぁ。
妄想をしながら、いつしか私は中学時代のT先生のことを思い出していた。中学一年生の担任は、自分が音楽の先生だったこともあり、私たちにやたら合唱を練習させようとしていて、2日に一度はピアノを弾いてクラス全員で唄うことが習慣になっていた。中学生活に慣れ始めた初夏のある日。T先生は一生懸命にピアノを弾いて暑くなってしまったのだろう。着ていたジャケットを脱いで、あろうことか、それをピアノの上にバサッと置いたのだ。私はビックリした。音楽を専門にしている人が、大切なピアノの上に脱いだ洋服を置くだろうか。その当時から偏屈な性格だった私は、その瞬間から「この先生のことは信用しない」と心に決めた。
そんな思い出話からお隣の男性の行動を結論づけるとすると・・・。もしギターケースの中身が本物のギターだとしたら、そして男性がギター弾きだったとしたら、T先生とは比べようがないほどに楽器を愛おしく思っている人ということになる。このあたりで妄想は完全にタイプ1に決定づけられ、私の中でお隣は有名なギタリストとなっていった。そうなると、どんなジャンルのギタリストなんだろう、地味な雰囲気から想像するにスタジオミュージシャンじゃなかろうか、などと妄想はステージ2へと発展。そんな頃、新幹線は新横浜に停車し、件の有名スタジオミュージシャンはギターケースを大切に抱えながら、私に会釈をして去っていった。正直言って決してイケメンでもなく、若くもなく、一見したところはただのオジサンだというのに、楽器を愛おしんで使うギタリストというすり込みのおかげで、私は密かに赤面していた。
ぽぉ〜っとしたまま約10分が経ち、車体は再びスピードを落としてホームへとすべりこむ。新幹線を降りると、潮の香りがわずかに混じった生暖かい風が赤面していた私の頬を撫でた。いつもの品川の風だった。