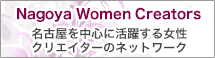天領のかおり【伝統工芸の職人たち】
高山では、左官職人・挟土秀平さんが連れていってくださったとある割烹にて夜を迎えた。とりたてて特色のなさげな、なんでもないお店。けれど、目を凝らして見ると、アンティークのランプや磨き抜かれたカウンターになんともいえない佇まいがある。大将がお一人で切り盛りするお店で、次々と入るオーダーに実にてきぱきと仕事をこなし、お料理とお酒を仕上げていく。その手際の良さだけでなく、味も驚く程おいしいのである。特に書き立てるほどでもない、なんでもないお料理。たとえば飛騨のあげを炙ったものに、醤油と大根おろしをつけていただくもの。ところがこの飛騨のあげが格段に味わい深く、醤油がまたコクのあるおいしいお醤油なのだ。秀平さんは他のお客さんのオーダーが混んでいない頃合いを見計らって、大将にお酒や料理の注文をいれる。大将も我々の食べ方を見ながら、決してお箸が休むことのないよう気づかいつつ、料理を出してくださる。この抜群の間合いはなんなんだ!
さらに大将は、お客さんの会話にするりとうまく入り込む。シュールレアリズムという言葉を発した時、「福沢一郎」の話をし始めた。日本酒を吹き出してしまうかと思う程驚いた。音楽にしたってそうだ。あれだけ忙しそうに料理しているのに、お客さんの会話や雰囲気に合わせて選曲し、大将セレクトのMDでBGMを流しているのである。一体何者なんだろう、この大将は。
時計が九時半を過ぎると、お食事のお客さんがお帰りになり、飲むお客さんがぞろぞろと入ってくる。秀平さんによるとここは「学習割烹」だと言う。高山の知識人が集まるサロンなのだと。ここで語り合い学んだことが仕事に結びつき、悩みを解決し、表現者としての活力を得ているらしい。次々とのれんを分けて入ってくる人を見て「あ、この人は大関」「この人は横綱や」とコメントがつく。秀平さんは、このお店では前頭筆頭なのだそうだ。先生と呼ばれる人、建築家、職人、職業はさまざまである。ここで語られるのは、文学、美術、建築、音楽、映画、小説、郷土史と、無限大に会話がひろがってゆく。
ここはまるで60〜70年代のパリである。サルトルやボーヴォワールが語り明かしたサンジェルマンのカフェである。ワインの代わりに日本酒を飲み、チーズの代わりに飛騨の漬け物をかじる。それぞれの知識と欲望を交錯させながら、刺激を与え合う。酔いの心地よさとぴりぴりした知的好奇心の中で、これはパリ以外のどこかで味わったことのある感覚だと思った。
それは倉敷だ。確か倉敷を訪ねた時にも同じような感覚を覚えたのだ。一地方都市でありながら、とてつもない底力を土地の人の会話から感じ取ったのである。その街で生まれ育ったことに誇りを持っている。その街から全国に向けて文化を発信しているという自負がある。そしてそれが実際に多くの文化財を生み出してきている。そして、よくよく考えてみると、倉敷と高山、2つの街に共通しているのは、天領地だったということだ。
江戸時代の幕府直轄領のことを天領と呼んでいた(実際に天領という名がついたのは明治になってかららしい)。天領になるということは、つまりそこに莫大な富を生む産業があるということで、豊かな土地の証である。倉敷のとある老舗旅館の大女将が「倉敷は天領の地ですから、こういう考えの人がおおございますの」と言っていたのを思い出した。こういう考えとは、"富んだ者がその土地の人のために文化交流の空間を提供する"ことで、それは倉敷の場合、大原美術館のことを指していた。
先のコラムで紹介した挟土秀平さんの洋館も、いずれは大原美術館のように後年の人々を魅了してやまない空間になるだろう。物質的に富んでいるかどうかはともかくとして、少なくとも精神的にはかなり富んだ人が集う「学習割烹」。その末席にひとときでも加われて、この夜は満足して帰路についた。そうそう、帰る時の大将のおはからいにもびっくりした。前夜ほとんど寝ていなかった私は、日付が変わった頃に酔いと共に眠気が襲い、はからずも二度ほどあくびをかみ殺したのである。三度目のあくびを飲み込んだ時、秀平さんの目配りで大将がタクシーを呼んでくださった。細かなところに目線が行き届く「職人芸」には、とてもかないそうにない。